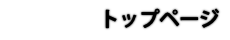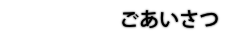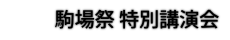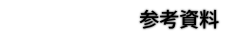4. 新制大学の教養教育における初期構想からの乖離
これからの教養教育とは、イギリス型とアメリカ型の両方を採り入れて、そして全体として“ゆとり”を持って人間性を伸ばすような教育をするということ・学生を存分に遊ばせるということである、というふうに南原さんはあの本の中で語っているわけですが、実際にここ駒場で実現している教養教育はどうかというと、ものすごく“欠け”ています。後から説明があると思いますけれども、「存分に遊んで人間性を伸ばす」というような側面はないんです。イギリス型紳士教育の側面も全くありません。アメリカ型の教養教育に近い部分は多少はあります。ですが、制度が大幅に違うおかげで、それも十分ではないという状況にあるわけです。今日、皆さんがこの会場(編注:講演が行われた18号館は、駒場キャンパスのなかでも比較的奥まった場所にある。)に来るまでに、正門からいろんな所を通って来て、駒場祭の様子をご覧になって、とても教養がある学生がやっていることとは思えないでしょう? もはや駒場祭は、これほど馬鹿みたいなことをやって、ほとんど食い物を売っているだけなんですね(笑)。こういう所に来て、ちゃんと中身のある話をまじめに聴くというようなことは少なくて、この講演だけではなく他にも多少はありますけれども、ほとんどがあれなんです。「人間性を伸ばすために遊ぶ」空間ではなくて、「人間性を伸ばさない方向で遊ぶ」連中の、一種の“ZOO”のような所になっていて、先ほど述べたような要素が、ものすごく欠けているんです。
そしてもう一つ、南原さんは先ほどの『回顧録』の中で、教養学部は基本的に、とにかくいろんな学問からそれぞれ極めた人が出てきて、その人が大所高所からメッセージを発するような授業が並ぶ、そういうものとして教養教育を構想した、と言うんです。ところが、現実にその後どうなったかというと、『回顧録』が出たのは、南原さんが東大を退官してからずっと後の時期なんですが、南原さんが反省としてどういうことを言っているかというと、「本当はこういう形で構想したのに、教官として教養学部で実際に授業をする先生方は若い人たちばっかりになってしまった。学問の道をそれぞれの分野において極めた碩学のような人が若い世代に重要なことを教える、という要素はほとんどなくなって、若い研究者の養成所になってしまった。これは全くの計算違いである」というようなことを、『回顧録』の中で語っておられます。
僕自身の意見としては、碩学も若い研究者も両方必要だと思います。若い研究者の養成所のような役割もやはり教養学部の教員組織として果たさなければならないだろうし、現実にも果たしてきていると思うんですね。でも、そこの所はものすごく微妙なところでして、若くても中身のある人ならいいんですよ。ただ学生は教員を見分ける力が結構ありますから、「教える力も教える中身も乏しい」と学生に見抜かれてしまうような若い研究者の先生が少なくないんです。
そういう教員たちは僕が学生をしていた頃からいまして、本当に学生から馬鹿にされます。『逆評定』(※『逆評定』の冊子が会場のスクリーンに映る。)表紙に「崖の上のポニョ」ではなくて「崖の上の大鬼」と書かれています(笑)。これは何かというと、これは学生が自主的に作っている冊子で、時代錯誤社という名前で出していますが、要するに学生が勝手に作っている、教官の逆評定なんです。一人ひとりの先生がどういう先生で、ということが書いてあります。例えばこの項目は、「指導は熱心」とか、ページの上の方にはマルだのバツだので教員に対する評価が書いてあるんです。「鬼」とか「仏」とかいう表記もありますが、これは試験の辛さなんですね。先生はどういうふうに学生を評価してくるか、なども書かれていて、ABCDで評価されたりもして、この冊子に載っているんです。こういうものを生む教養学部の現状というのは、かつての師弟関係では考えられないことだったわけで、こういうものが生まれ、それを学生が皆利用しているということ自体は大学のカルチャーの変化として面白いとは思うんですが、実はものすごく問題があるということを、また後で話したいと思います。