| 見聞伝 > 戸塚洋二の科学入門 > 科学入門シリーズ 4 |
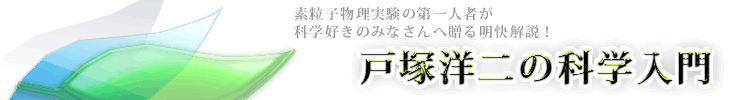 |
科学入門シリーズ4
19世紀末 科学の困難 光の科学
第8回 コンプトン散乱、X線も粒子
1900年、マックス・プランクは、光はツブツブである、という光の量子説を発表しました。永らく光は波と考えられてきたので、多くの科学者は光量子説を認めようとしませんでした。光量子(光子)説が確立されるためには、その説を支持する新しい現象を見つける必要がありました。つまり、世間が革命的なアイディアを認めるためには、多くの観測事実が必要なのです。このことは、現在でも変わりません。
るつぼ内の光の現象と光電効果は、光量子説の正しさを証明していました。さらにもうひとつの現象が光量子説を証明したのです。それが今日話す「コンプトン散乱」と呼ばれる現象です。
コンプトンというのは、アメリカの物理学者の名前、アーサー・コンプトン博士に由来します。1892年の生まれですから、プランクが光量子説を発表したときはまだ8歳でした。プランクが活躍したのは1920年代前半ですから、プランクから20年後。まだまだ光量子の研究は活発に行われていました。
コンプトンが注目したのは、波長がすごく短い(振動数がすごく高い)電磁波のX線です。物質の結晶を使った精密な分光計が開発され、X線の振動数や波長も精密に測れるようになっていました。
もし、光が分子のようにツブツブの光子と呼ばれる粒子なら、光子1個1個を取り出し、標的にぶつけてみたらどうだろう。標的は蹴飛ばされやすいように軽いほうがよいだろう。ベストなのは、物質中にたくさんある電子がよい。光子の振動数またはエネルギー(E=hfを思い出そう)が高ければ、ぶつけられた電子は遠くまで蹴飛ばされるだろう。下に光子と電子の玉突きを漫画で示しました。
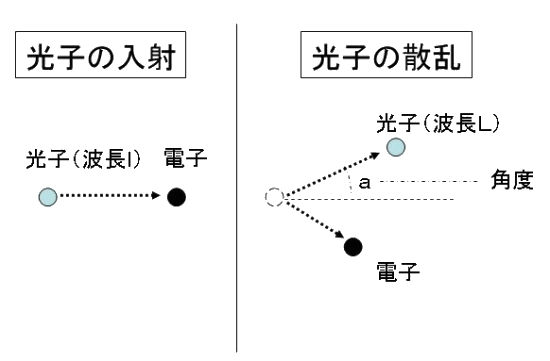
高校の理科で、エネルギーと運動量の保存という法則を聞いたことがあると思います。図のような玉突き反応を分析するにはエネルギー・運動量保存の法則を使います。しかし、光のエネルギーはhfでしたが、運動量はまだ説明していません。アインシュタインの相対性理論を使うと、光の運動量は、
hf/c
となります。ここで、hはプランク定数、fはX線の振動数、cは光速です。
コンプトンは、1923年の論文で、X線(光子)と電子のぶつかりを計算し、さらに論文の続編で、実際に実験をしてその答えを発表しました。
大切な点はこうです。X線が光子として電子を跳ね飛ばしたとしよう。電子は運動エネルギーをもらうのだから、X線のエネルギーはその分だけ減るはずだ。X線のエネルギーはhfだから、X線のエネルギーが減れば、その振動数fは小さくなる。振動数の減り方は、X線が跳ね飛ばされる角度によって変わるだろう。また、波長はc/fだから、逆に跳ね飛ばされたX線の波長は長くなるはず。
コンプトンの式は簡単ですから書いておきましょう。入射するX線の波長をl(ローマ字のエル)、跳ね飛ばされたX線の波長をL、跳ね飛ばされる角度をaとすると、
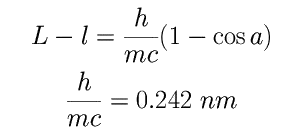
となります。ここで、mは電子の質量です。nmはナノメートル(10億分の1メートル)のことです。
(入射するX線の何%が散乱されるのかも知りたいところですが、この式は日本の仁科芳雄博士とドイツのオスカー・クライン博士によって1929年に求められました。仁科博士は当時デンマークの偉大な科学者、量子力学の創始者のニールス・ボーア博士の下に留学していました。仁科博士は39歳でした。)
コンプトンは、実験のためにモリブデン電極を使った強力なX線管を自作しました。X線管によって、モリブデンのKアルファ線といわれる波長7.11ナノメートルのX線を発生させます。このX線を炭素の板にぶつけ、45°、90°、135°の角度で跳ね返ってくるX線の波長を精密に測ります。炭素の中にはたくさんの電子がありますから、X線の一部は電子に跳ね飛ばされて波長が伸びたX線が混じっているはずです。
ちょっと専門的ですが、コンプトンの論文からデータをお見せしましょう。当時の実験ののどかさが伝わってきます(一般の方にはわからないかな)。ちょっと図が汚いのですが我慢してください。図の中のポツポツが観測したデータです。横軸は波長をあらわします(単位は分光系の角度ですが無視してください)。4つの図からなっていますが、図Aは入射X線の波長分布です。図B,C,Dはそれぞれ散乱角aが45°、90°、135°のときのデータです。図の中の線はデータをなぞった線であまり意味がありません(現在はこんな線は描きません)。図に2本の縦線P、Tが引かれています。左側の縦線Pは入射X線のピークで、右側の縦線Tは波長が長くなった散乱X線のピークです。右側のデータと縦線Tを見ると、確かに、散乱角が大きくなるにしたがって波長が長くなっています。
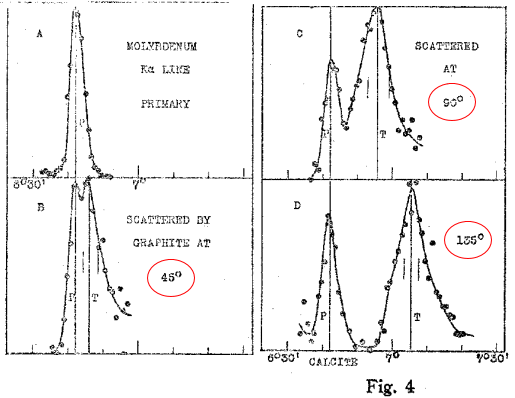
この論文では、横軸の値を波長に換算して上のコンプトンの式と比較した結果は論文には出ていませんが、「波長が散乱角とともに長くなる度合いは理論が予想するようになっている」とだけ書いてあります。とにかく、予想通り波長の長くなったX線が飛び出してくるのは確かめられました。(実験の第一報ですからしかたがないでしょうが、現在だと、この程度の論文は掲載を拒否されますね。)
この実験結果は、X線、つまり電磁波が一つ一つの粒子となっていて、その粒子が炭素中の電子と散乱したことを証明しています。その後、コンプトンは、散乱されたX線と一緒に跳ね飛ばされた電子も観測する実験を行い、X線と電子の散乱をさらに詳しく研究しています。
1927年、コンプトンは自分の名前のついた発見(コンプトン散乱)によってノーベル物理学賞を受賞しています。35歳のときです。功成り名を遂げたコンプトン博士は後年マサチューセッツ工科大学(MIT)の学長になっています。
以上、長々と「光が粒子」だという革命的なアイディアとその実験を説明しました。1890年代から1920年代までの物語です。ヘルツ、プランク、アインシュタイン、ミリカン、コンプトンという当時の科学界の巨人が活躍した時代です。アメリカ人が科学界に進出を始めた時代でもあります。
この時点で、光量子説を疑う人はいなくなりました。
現在では、X線よりもずっとエネルギーの高いガンマ線の研究で、文字通り1個1個の光子の反応を見ることができます。下の写真をご覧ください。
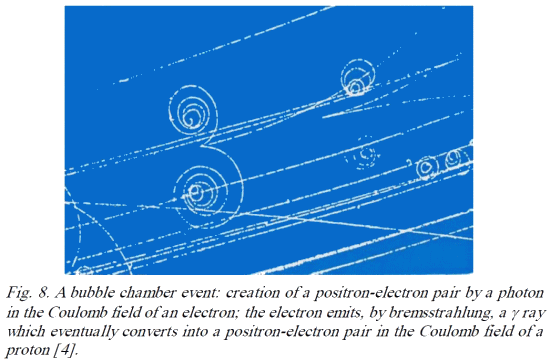
(http://arxiv.org/vc/physics/papers/0604/0604152v1.pdfより引用。)
泡箱と呼ばれる装置で粒子の飛跡を見ることができます。左から右上にちょっと曲がった直線が何本か写っています。これらは電気を持った粒子の飛跡です。真ん中あたりに2個の渦を巻いたような飛跡があり、その延長線上、右中央に狭いV字型の2本の線が生まれています。これらの飛跡は、左からエネルギーの高いガンマ線が入ってきて(ガンマ線は電気を持っていないので写真に写らない)原子と反応し3本の電気を持った粒子を発生しています。同時に写真に写らない1個のガンマ線も発生し、それが右に飛んで、さらに2つの電気を持った粒子に変わっています。
以上でこのシリーズを終わります。
|
|
| Copyright (C) 2008 戸塚洋二, 東京大学 立花隆ゼミナール All Rights Reserved. 表示が崩れますか? |
|